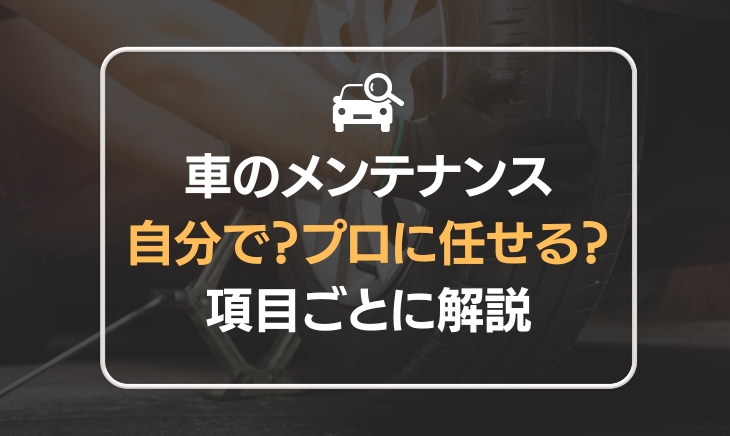車のメンテナンスは、意外と自分でできるメンテナンスも多く、車の知識がなくてもちょっとしたポイントをおさえれば簡単に行えます。
また、一方でどうしても自分では難しく、整備工場にお願いすべき整備も存在します。
この記事を最後まで読んでいただき、「自分でできる・プロに任せるべき」なのか見極める判断材料として活用して下さい。
車のメンテナンスの優先順位
近年の車は、精度や耐久性の向上により10万kmを超えても全く問題なく走れる時代と言われていますが、それは適切なメンテナンスとセットで語れるものです。
ただメンテナンスといっても、車には多くの点検箇所が存在します(ちなみに車検時の法定点検は56項目あります)。
ここからは「まずどこを優先してメンテナンスするべきなのか」について解説します。
優先1:窓ガラスの清掃

| メンテナンス頻度 | 2週間に1回程度 |
| メンテナンス方法 | 洗車、拭く、ウィンドウコーティング |
メンテナンスといえば「エンジンオイル交換、タイヤの空気圧点検など」がまず頭によぎりますが、筆者は窓ガラスのメンテナンスが最優先だと考えています。
「窓ガラスを綺麗にしておく」というのは、見た目の綺麗さ、衛生面だけでなく、安全面においても重要な役割を担っています。
車はちょっとした操作ミスや判断ミスが大事故につながるため、「そもそも事故を起こしにくくしておく」ということはドライバーとしての基本です。
運転はよくスポーツに例えられます。
サッカーを例にすれば、敵がどこにいて、ボールがどこにあるという情報を得て、点を取りに行くためには次にどうするかを判断し、動いたりボールを蹴ったりします。
運転も同じように周りのクルマがどこにいて、信号や標識を確認し、次にどうするかを決めて、ハンドル、アクセル、ブレーキを操作します。
「正確な情報を得る」というのは、スポーツに限らず、運転する上でもっとも重要なことと言えます。
優先2:エンジンオイル交換

| メンテナンス頻度 | 5000km毎 or 6ヶ月毎ごとの交換 |
| メンテナンス方法 | 指定オイルの交換 |
エンジンオイルとは、エンジンに使用されている潤滑油であり、車の消耗品の中でも最も交換する頻度が高く、これを怠ると「長く乗る」ことはできないと思って下さい。
エンジンはとても重要な部分であり、人間に例えれば「心臓」です。
心臓は血液が無いと機能しませんが、エンジンも血液にあたる「エンジンオイル」が無いと全く機能しません。
「エンジンオイル=潤滑」というのはイメージしやすいかと思いますが、他にも以下の役割があります。
| 密封 | シリンダーとピストンを完全に密着させる |
| 冷却 | エンジン各部の回り熱を吸収する |
| 洗浄 | 様々な汚れ(スラッジ)を取り込む |
| 防錆 | 外気温差などによる水分の発生を抑える |
エンジンオイルは、ただの「油」でななく、さまざまな効果でエンジンを守っています。
エンジンオイルは使用するにつれて「すす・酸化物・熱・ブローバイガスの混入」などによって、汚れ、劣化していきます。
また、使用していなくても空気に触れることによって酸化し劣化もします。
その他の要因として「エンジンオイル自体の温度=油温」があります。
エンジンオイルの温度は高すぎても、低すぎてもよくありません(適正温度は90℃~120℃と言われています。)
渋滞やスポーツ走行などで、油温が上がり過ぎることや、逆に近所までの買い物や送り迎えで油温が低すぎる状況は、エンジンオイルの性能を劣化させる大きな原因となるので、負荷をかけるような運転が多い人は早めの交換を行うように心がけましょう。

まだ購入して間もない新車で交換を怠っても、さほどエンジンの調子は変わりませんが、これが何度も続き、走行距離10万kmオーバーになってくるとコンディションの悪さがあらわになってきます。
距離が増えていくにつれて後で後悔するような故障が待っていますよ。
すぐに乗り換える予定なら別ですけどね。
エンジンオイルは、エンジン自体の耐久性を大きく左右する大切な消耗品なので、それぞれの車の取扱説明書に記載されている「推奨される交換時期の距離と使用期間のいずれかの早い方、シビアコンディションの場合はその半分」で交換するようにしましょう。
優先3:バッテリーの点検

| メンテナンス頻度 | 6ヶ月に1回 |
| メンテナンス方法 | 専用のテスターによる診断 |
運転していると「車の調子」って気になると思いますが、何を中心に気を付けていますか?
タイヤやオイルなどは結構気になるのですが、意外と優先順位が低いのがバッテリーではないでしょうか。
運転する上でもっとも大事なことってなんだと思いますか?
まずは安全にエンジンを掛けるという行為ではないでしょうか。
スタートボタンを押すと、スターターモーターによってエンジンを回転させ(クランキング)始動させる。
大昔のクルマは外から手動でエンジンを回して始動していましたが、今は電気の力を使ったモーターを使うため、バッテリーに不具合があると、そもそもクルマは動くことができません。
JAFの救援要請では、バッテリーとタイヤ関係のトラブルが全体の50%以上を占めています。
もうひとつ、重要な役割がバックアップ。
イグニッションをオフにした駐車時でも、時計やオーディオ類の設定、さらに現代のクルマはエンジンを制御するコンピュータもエンジンの状態などをメモリーし、燃料噴射などを調整しています。

バックアップにはバッテリーの電力を使用しているので、完全にバッテリーが上がるとリセットされてしまい、再度コンピューターに学習させる必要があります。学習をさせずに走行すると、エンストやアイドリング不調の原因になります。
このように、エンジンで動く自動車にとってバッテリーは重要な役割を担っています。
また現在のバッテリーは技術の進歩もあって、ギリギリまで性能を維持して突然死ぬという現象を起こします。
日頃の点検が大切です。
バッテリーの突然死問題については、以下で解説しています。
優先4:タイヤの点検

| メンテナンス頻度 | 月1回 |
| メンテナンス方法 | 空気圧チェック、外観のチェックなど |
車とは「タイヤが4つ付いている乗り物」であり、状態の悪いタイヤの性能を使うと車の性能はダウンします。
最低でも月に1回の空気圧チェックは実施しましょう。
タイヤは、車の性能を路面に伝える最後の部品。
「走る・曲がる・止まる」の3台要素をすべて担っています。
どれだけハイパワーのエンジンを搭載したとしても、どれだけ性能の良いブレーキを装着したとしても、タイヤがダメだと台無しです。
いくら足が早くても、サンダルで走ったら100%の走りは発揮できませんよね。
優先5:エアコンの効率化

| メンテナンス頻度 | 年に1回 or 1万kmに1回 |
| メンテナンス方法 | 冷媒圧のチェック、エアコンフィルターの交換など |
カーエアコンはスイッチ1つで夏も冬も晴れの日も雨の日も車内を「快適温度」と「快適湿度」に変えてくれるとても便利な電装品です。
しかし、カーエアコンにはクルマにとってデメリットが多いです。
それは作動時にエンジンにかかる負担が大きい(回転数が上がる)ということ。
つまり燃費に影響するということです。
家庭用エアコンでも「エアコンを使うと電気代が…」という人が大半だと思いますが、これはコンプレッサー(冷媒ガスを圧縮する装置)の稼動時間が多いことが原因で電気を多量に消費してしまうということになります。

カーエアコンも同じで、コンプレッサーが稼動する時間が長ければ長いほどエンジンに負担がかかり、燃費が悪くなります。
家庭用エアコンでもカーエアコンでも勘違いされている方が多いようですが、エアコンを弱い状態で長く使うよりも、一気に室温を下げ、エアコンを停止させてその室温を維持する方法の方が燃料を節約できることになります。
理由としては、エアコンを弱めても設定温度に達しない限り「コンプレッサー」が稼動してしまうから。
エアコンのコンプレッサーは、コンピューターが外気温センサー、内気温センサー、日射センサーなどの各センサーの温度を元にエアコンシステムを制御して、ドライバーが任意で設定した温度に近づけます(オートエアコン車)。
なので、仮にエアコンフィルターが詰まっていたとしたら車内がなかなか冷えないので、コンプレッサーは駆動→ブロアファンが全開で駆動→余計な電力が必要となるわけです。
燃費に直結するエアコンをできるだけ効率良く稼働させるためには、エアコンのメンテナンスは欠かせません。
つまり、車内を冷やしやすくしておくことでコンプレッサーを駆動を抑えれるという考えですね。
エバポレーターの掃除、エアコンフィルターの定期交換などは、衛生面にも関わる部分ですから気を配りましょう。
エアコンの効率化については、以下で解説しています。
優先6:洗車

| メンテナンス頻度 | 週1回 |
| メンテナンス方法 | 手洗い、洗車機 |
洗車をすると車をていねいに扱うようになります。
ブロークンウィンドウ理論という考え方をご存知でしょうか。
アメリカの犯罪心理学者の理論で、窓ガラスが割れた建物では犯罪が起こりやすいというものです。
ニューヨークの地下鉄は以前落書きだらけで犯罪が多発していたが、落書きをキレイにしたら犯罪が激減したというのです。
よくある話では、新車で買って大切に乗っていたものの、擦ってしまい「傷物」になった途端、安全運転を気にしなくなったと。
キレイを保つということは、事故を起こさない・事故に遭わない為に、周囲に気を配り、自身も安全運転を意識するようになります。
交通事故は運転時の心理面も重要な要素なので、キレイにするだけで安全運転を気にかけれるならそのほうが良いですよね。
自分でできる車のメンテナンス
ここからは、自分でできる車のメンテナンス方法についてご紹介します。
1:窓ガラスの清掃
窓ガラスのメンテナンス方法は、以下で解説しています。
ウィンドウコーティングのおすすめについては、以下で解説しています。
2:洗車
洗車のおすすめグッズについては、以下で解説しています。
3:ワイパーラバーの交換
もし雨天時に「拭き取り具合が悪いなぁ」と感じたら、以下の3点を確認しましょう。
ひとつでも当てはまる場合は、ワイパーラバーの交換時期です。
4:ウォッシャー液の補充
4:タイヤの空気圧チェック
少なくとも1カ月に1回くらいは空気圧の点検を行うようにしましょう。
タイヤの空気圧は目視しただけではどれくらい減っているか正確に判断できないので、必ずタイヤ空気圧を計測するゲージで測定しましょう。
5:エアコンフィルター交換、エバポレーターの掃除
エアコンフィルターの交換方法は、以下で解説しています。
エバポレーターのメンテナンス方法は、以下で解説しています。
6:バッテリーの点検
バッテリーの点検方法は、以下で解説しています。
プロに任せるべき車のメンテナンス
ここからは、自分でできる車のメンテナンス方法についてご紹介します。
1:エンジンオイル交換
エンジンオイル交換は、簡単そうに見えて注意する点が多いため、プロに任せましょう。
エンジンオイルを自分でするメリットは自分で選んだこだわりのエンジンオイルを使えるところです。
また自分でエンジンオイル の交換作業することで、より一層愛車への愛着も深まります。
一方自分で交換するデメリットはオイル交換のための道具をいくつか揃える必要があり、誰でも気軽に挑戦できるほど手順が簡単ではないことです。
また廃油も責任をもって地域指定の方法で処理する必要があります。
オイル交換を自分ですれば工費を節約できると考えているかもしれませんがカー用品店やガソリンスタンドに頼んでもオイルの料金と工費を合わせて3,000〜7,000円程度です。
また道具をそろえないといけないことを考えると、自分でのオイル交換はあまり費用の節約にはなりません。
2:タイヤ交換
タイヤ交換は、失敗すると重大な事故につながるため、プロに任せることをおすすめします。
タイヤは車にとってとくに重要な部品であり、作業に不備があれば事故につながりやすい箇所です。
そのため、タイヤ交換を行うには手順を知っているだけでは不十分。
より安全な作業を行うためには、作業手順の意味を深く理解しておく必要があります。
部分的な車の構造をはじめとして、ホイールナットを緩めるタイミングや締め具合、交換作業をしてはいけない場所などを知っておかなければ、ケガや事故に加え、車を破損させるリスクが高まります。
3:ボディコーティング
ボディコーティングは、DIYでできる商品が充実してきているので悩みますよね。
まず最初に「プロに施工してもらうか」・「自分で施工するのか」を明確にしておきましょう。
それぞれの特徴をまとめると以下の通り。
| プロに施工してもらう | 自分で施工する | |
|---|---|---|
| メリット | しっかり施工できる アドバイスを受けれる | 値段を抑えられる 店に行かなくて良い ネットで買える |
| デメリット | 値段が高い 店に預ける必要がある | 知識・道具が必要 手間がかかる |
| 向いている人 | クオリティ重視である | コスパ重視である |
ポイントは、「仕上がり重視なのか・価格を抑えたいのか」というところかと思います。
基本的な考え方としては、完全初心者であれば「施工店」、ある程度の経験・知識があるのであれば「自分で施工」が良いと思います。
ここで言う「ある程度の経験・知識」は、手洗い洗車派でウィンドゥコーティングなども自分でやっている、いわばクルマのボディと触れるのに慣れている人を言います。
そしてコーティングは、材料の品質、施工の手順、作業する道具によってクオリティが左右されます。
なので完全初心者が自分でやると言うのはハードルが高いです。
コーティングは施工を失敗すると、剥がすのに結構な労力が必要になりますので、それなりの覚悟が必要です。
だからプロがいるわけなのですが、値段をできるだけ抑えたい人もいるはず。
しっかりとした知識と、施工手順を守れば自分で施工することは全然可能なので、取り扱い説明書をよく読んで施工するように心がけましょう。
車のコーティング剤のおすすめは、以下で解説しています。
スバル車乗りにさらに伝えたい「長く乗るコツ」
ここまで書いたメンテナンスはいわば「基本中の基本」。
ここからは、現在スバル車に乗られている人に向けて、「愛車とのさらなる向き合い方」をお伝えします。
走行距離10万kmがリフレッシュの区切り

気を付けたいポイントとしては、点火プラグ、燃料ポンプ、燃料フィルター、ウォーターポンプといった定期点検ではあまり手の入ることのない場所にも気を配って頂きたい点です。
EJエンジンであれば、タイミングベルト周りのアイドラ、テンショナー、ウォーターポンプなどの周辺パーツは交換必須です。
これらのパーツは、ガソリンエンジンの基本3要素である「良い火花・良い圧縮・良い混合気」に関わってくるパーツであり、高速走行中に故障した場合はオーバーヒートやエンジンブローの原因にもなるため事前に交換しておくようにしましょう。
ちなみにタイミングベルト、点火プラグ、燃料フィルターは、メーカーも10万km定期交換部品としても指定しています。
現代のエンジンは昔と比べて故障のリスクが減っていますが、機械部品や電子部品の塊ですから、予期しない故障やトラブルが絶対ないとは言えません。
また、5万kmを過ぎた頃からクルマの足回りに腰砕けた感じが出てきて、「コトコトガタガタ」とどこからともなく音がしてきたり、「なんか乗り心地が悪くなってきたなぁ…」と感じているオーナーさんは、足回りリフレッシュも考えてみてはいかがでしょうか。

「新車時の乗り心地を維持できるのは6万~7万km程度まで」とよく言われます。
ダンパー4本交換される人が多いですが、アッパーマウントやサスペンションの各種ブッシュ、ロアアームブッシュといったゴム類も検討しましょう。
ダンパーだけ新品にしても、足回りのアーム類のブッシュが硬くなったり、ひび割れたり、動かなかったり、動きすぎたりしてしまうと、シャキッとした足回りは実現しません。
「アーム類のブッシュを交換する=人間の関節を新品に交換する」といったイメージです。
ディーラーの保証制度はうまく使って欲しい

新車で購入した場合、国内に販売されているすべての正規販売車であれば、必ず保証が付帯しています。
いずれも期限や距離が定められ、それを超えた場合は有償でのメンテナンスとなります。
| 一般保証 | 特別保証 | |
|---|---|---|
| 期間 | 3年、6万kmどちらか早いほう | 5年、10万kmどちらか早いほう |
| 代表例 | エアコン、パワーウィンドゥ、ドアミラー等 | エンジン、ブレーキ、ハンドル等 (走行に直接関わる部品) |
この保証は、正規販売で購入する最大メリットであると考えており、長く愛車と付き合っていくのであれば、ぜひ活用して頂きたいところ。
複雑な中古車保証よりも内容が強力ですし、専門の教育を受けたディーラーメカニックによる正確な故障診断と部品交換作業を受けられます。
ただこの期間に該当するすべての車両に対して反映されるわけではありません。
改造車やサーキット走行によって、故障箇所への負荷があったと判断された場合は保証が受けられなかったりします。
また、ディーラーが指定している定期点検をしっかり受け、十分メンテナンスされていることが前提なので注意して下さい。

クルマには車種ごと部品ごとに弱点があったり、年改が浅い新型車の場合はリコールや改善対策に該当しない「潜在的な初期不良」もあるので、保証期間中に気になったことは積極的に問い合わせるようにしましょう。
こういった問合せは、新型車開発・年次改良に生かされていきますので、貴重な意見となります。
エンジンオイル漏れとの付き合い方

「水平対向エンジンはオイル漏れしやすい…」
これは昔からよく言われます。
一般的な直列エンジンでは、ガスケットは基本的にエンジンの横方向に広がっており、オイルはその脇を流れ落ちていくような形になります。
オイルがガスケットに触れている時間はほんのわずかなので、重力やエンジンの動きによってオイルは断続的にガスケットに当たるような構造です。
水平対向エンジンの場合は、横置きのエンジンになりますので、オイルがガスケットの下側の位置に溜まる結果となります。
重力で自然に流れてはいかないので、なにかしら動くものがない箇所はオイルが常にガスケットに接触している時間が長くなるわけです。
簡単に言うと蓋をしたペットボトルを横向きにし、水平に倒した状態と縦向きに置いた状態では、どちらが漏れやすいのか、といったイメージでしょうか。
ただ、「ガスケット類の品質と向上」や「エンジンオイルの品質向上」、「ゆとりのあるエンジンルームによる熱ごもり軽減」によって一昔前に比べるとオイル漏れ修理も減少傾向にあります。
20年以上前の水平対向エンジンは、車検ごとにオイル漏れ修理を行っていたという話もよく聞いてました。
そこで自分がやってきた対策としては以下が有効だと思われます。
エンジンオイルの漏れを遅らせるには、エンジンオイル交換が重要です。
オイル漏れの主な原因は、経年劣化したパッキン(ゴム)が硬くなり、伸縮性がなくなるので、オイルを支えていた部分に隙間ができ、そこからオイルが漏れだしてしまう、というパターンが大半です。
さらにオイル交換をサボると、オイルラインに蓄積する不純物が循環することでさらにパッキン類を傷めてしまいます。
スラッジが溜まる前に劣化したエンジンオイルを排出することで、パッキンの寿命を極力伸ばすことができるはずです。
次に「高負荷運転後のクールダウン」なのですが、クーラント温度と油温をガンガン上げた状態でエンジンを切らないということです。
高負荷運転をした直後では、エンジンルーム内全体に蓄積した熱量が大きいです。
エンジンを止めることでウォーターポンプが止まり、クーラント温度が局部的に上がり続けます。
ゴムパッキンや液状ガスケットは、どうしても高温状態には弱いので、これを少しでも意識するだけでも変わってきます。

まとめると、オイル交換の頻度は3000~4000km毎、高負荷運転後はアイドリングさせてからエンジンを切る、もしくは目的地に着く前に低負荷運転による走行風で冷やすなどを意識すると良いです。(あくまで持論なので参考程度で)
スバル車の故障については、以下でも詳しく解説しています。
カスタムはどこから!?初心者が注意すべき点

量産車は、どんなにこだわって選んだとしても自分と同じ仕様のクルマに出会うことは避けられません。
そこで「ほかとは違う」クルマに仕上げるべく、愛車に改造を加える「カスタム」とか「チューニング」を行う人が多く存在します。
走行性能の強化やドレスアップするなど、その目的はさまざまですが、「世界に1台しかないクルマに仕立てたい」という狙いはクルマを改造する人全員に共通していることかと思います。
ただ、初心者にとってカスタムをどこから始めればいいのか?
また、初心者はどんなことに注意してカスタムをしたらよいのでしょうか?
保安基準の知識は「ある程度持つべき」

クルマに関連する法律といえば「道路交通法」が有名ですが、カスタムをする上で切っても切れない存在が「道路運送車両法」。
道路運送車両法は、自動車や原動機付き自転車、軽車両などの自動車運送車両の登録や保安基準、点検、整備、検査などについて定めた法律です。
その中でも保安基準は、クルマの構造や装置が技術上、最低限度の基準を定めた法律。
目的としては「クルマの安全確保および環境保全」。
保安基準に適合していないと「不正改造」とされ、6ヶ月以下の懲役または、30万以下の罰金という罰則を受けることになります。
例えば、「ランプを好きな色にしたい」や「ランプを追加したい」などの場合、色、高さ、位置、数、光度など保安基準を理解していないと、知らず知らずのうちに不正改造車となってしまうケースがあります。
こういう場合、保安基準スレスレのグレーゾーンだと自動車検査員によって判断が違ってきます。
国から認可を受けている整備工場側すると、不正改造を入庫させてしまうとペナルティを受けるケースがあるので、ディーラーによったら純正以外のパーツを装着していると断られることも…。
整備事業者もリスクを背負いたくないわけです。
なので、「このパーツは保安基準を満たしている」という証明をユーザー側からもできるようにしておくことが大切です。

また整備を依頼している人がほとんどだと思うので、カスタムする前に「そのパーツを装着しても入庫ができるのか」を事前に確認しておきましょう。
どこからカスタムすれば良いのか問題

たまに「どこからカスタムすれば良いのでしょうか」という質問をいただくことがあります。
カスタムする目的は人の数だけあると思いますが、根本的には「自分にとって足りない部分を補う」というのが目的だと考えます。
高速走行時にもっと安定感が…、コーナー侵入時での荷重が…、悪路での走破性が…、などなど、普段乗っていて感じているそのクルマの弱点が見えてくるかと思います。
もっとパワーが欲しければ吸気・排気系から始めたり、ハンドリング性能が欲しければタワーバーなどの補剛パーツ、走行安定性なら車高調や足回りパーツを交換するなど、そういった不満に持っている部分を自分なりに改善していくことが合理的なカスタムだと思ってます。
「純正なんかで乗ってるとか(笑)」みたいなマウントをとってくる人もいますが、愛車に不満がなければ純正で良いと思います。
「どこからカスタムしたら良いかわからない」というのは、まだ愛車の特性が理解できていないと思うので、走りながら感じ取っていきましょう。

「ラリーカー風にしたい」など、見た目から入るのも良いと思います。「カッコいい」というのは愛着が湧きますから。
スバル車のカスタム情報については、以下で解説しています。
カスタムパーツなら「モタガレ」がおすすめ

クルマのアフターパーツを通販で購入するなら最初にどう行動しますか?
- 実店舗なら「オート◯ックス、イエ○ーハット…」
- ネットなら「◯mazon、◯天、◯フー…」
- フリマなら「ヤ◯オク、メ◯カリ…」
こんな感じではありませんか?
そんな人にはぜひモタガレを利用して頂きたいです。
モタガレには、実に1500ブランド、35万点以上のカーパーツが掲載されています。
これは日本のクルマ系ECサイトではトップクラス。
これだけ品揃えが豊富なら、自分が欲しかったカスタムパーツを見つけることができます。
それ以外にも「あ、こんなパーツがあったんだ」と思える巡り合わせもあるかもしれません。
また、ホームページでただ商品を売るのではなく、取り付け店の紹介してくれます。
モタガレは、各イベントやオフ会の参加、取材を行なっており、適当に電話で契約したような取引先ではなく、実際に訪問したり、以前からのお付き合いがある安心できるショップを紹介してくれます。

モタガレは契約だけで右から左に商品をさばくのではなく、仕入先となるすべてのショップやメーカーに必ず脚を運び、顔を合わせて商品を取り扱っています。今まであったようで、あまり無い新鮮な取り組みですね。
モタガレについては、以下で解説しています。
まとめ

2020年以降は、クルマがすぐに手に入れない状況が続きます。
半導体不足、中古車相場の高騰、不景気などが掛け合わさり、販売側も購入側も頭をかかげる状況はいつ解消されるのか。
ここで重要になってくるのは、やはり「今の愛車を長く乗り続けるためにはどうすれば良いのか」ということがポイントになってきます。
販売店側もクルマが売れない状況にメドが立たないため、整備での売上を重要視してきています。単価を上げて売上を伸ばしたい整備事業者からの提案をしっかり分別し、愛車にとって的確なメンテナンスを受けるためにも「長く乗るコツ」はユーザー側も知っておくべきことです。